この記事では唐招提寺の歴史・建築の特徴を分かりやすく解説します。
鑑真とゆかりの深い奈良時代のお寺です。ぜひご覧ください。
見どころ・仏像解説記事
唐招提寺・鑑真の歴史を分かりやすく解説。

唐招提寺は759年、鑑真(がんじん)により建てられました。
朝廷から譲り受けた土地に、戒律を学ぶための寺を作ったのがきっかけ。
創建時には講堂など一部の建物でしたが、弟子の如宝(にょほう)が金堂などを建て、寺を完成させました。
唐招提寺の宗派
律宗(りっしゅう)
戒律の研究、実践に重点をおく仏教。
奈良時代に栄えた仏教、南都六宗の一つです。
鑑真の歴史
鑑真を知ることで、唐招提寺がより理解しやすくなると思います。
少し長いですが分かりやすくまとめたので、良ければご覧ください。

By Original: 俊武Later versions: Garam – 『世界史年表・地図』,
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93190959
鑑真は、688年に鑑真が唐の揚州で生まれました。
(揚州の場所は地図中の青い丸の中)
14歳で出家。
20歳で律宗・天台宗を学び、揚州の大明寺(だいめいじ)の住職になりました。
その頃、日本から栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)が遣唐使とともに唐に到着します(733年)。
なぜ栄叡と普照が唐へ行ったのか?
当時の日本は、仏教によって良い国にしようと、寺や仏を次々と建てていました。
そのための財源や労働力は農民から。
農民は重税と労働に苦しめられていました。
一方、僧には納税の義務がありません。
重税に苦しんだ農民らは、次々と僧になります。
特別な許可は必要なく「私は僧です」と名乗れば、僧侶になれてしまう(私度僧)
僧としての学びのない者がふえ、国や仏教の風紀が乱れまくっていました。
そこで聖武天皇は「授戒・じゅかい」を制度化する事を決意します。
授戒とは正式な僧になるための儀式です。
導師が「戎・かい」を授け、出家者は10人以上の僧の前で戒を一生守る事を誓います。
※戎とは、僧侶になるための決まり・いましめのこと。信者用の「菩薩戒」、正式な僧用の「具足戒」2種類ある。
唐には授戒の制度が整っていましたが、日本には導師すらいない状態。
聖武天皇は導師を求め、栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)を唐へ派遣しました。
無事、唐に着いた二人ですが、探せど探せどなかなか導師が見つかりません。
それもそのはず。当時日本へ行くことは命がけの行為の上に、出国は国から禁止されていました。
つまり2つの意味で命がけの密出国となります。
そんなリスクを犯して日本へ行く僧などいるはずもなく。
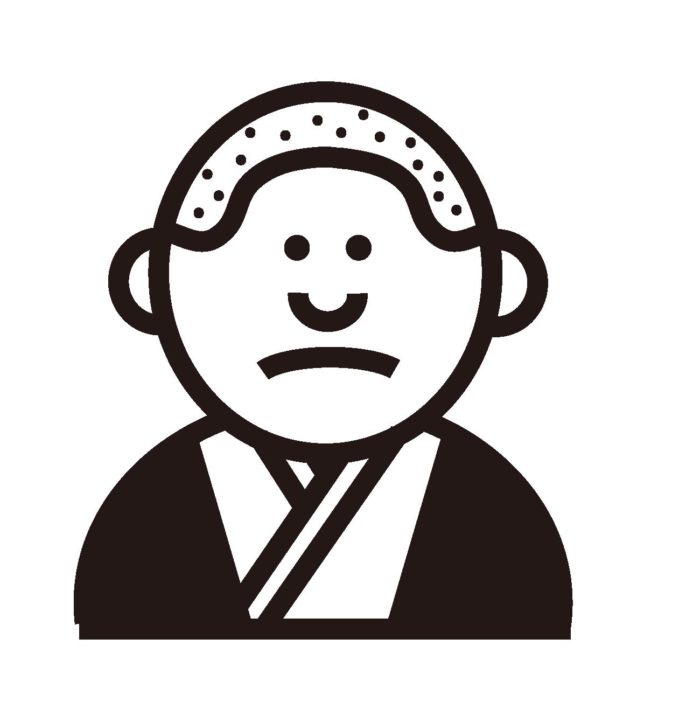
どこかに日本に来てくれる高僧はいないかなぁ…
探し続けること約10年。
途方に暮れる栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)は、一人の高名な僧、鑑真の噂をききつけます。
鑑真と出会ってからの年表
742年 栄叡と普照が鑑真のもとを訪れ、日本に来るよう懇願される
→鑑真(55歳)が日本へ行くことを決意!743年~ 日本へ行こうとするもたびたび失敗。鑑真は病にかかり失明する。
753年 6回目にして鑑真(66歳)が日本に到着。
大宰府観世音寺にて日本初の「授戒」を行う。754年 東大寺大仏殿にて授戒が行われる。聖武天皇など400名に戎が授けられた。
755年 日本初正式な授戒施設「東大寺戒壇院」を建立。759年 唐招提寺を建立
763年 76歳で亡くなる
742年、栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)は鑑真のもとを訪れます。
必死の説得に心を打たれた鑑真は、来日を決意。
しかし弟子の密告や悪天候により、たびたび失敗しました。
その間に栄叡が亡くなり鑑真は失明。困難を極めます。
なんとか日本へ辿りついたのは、約10年後の753年でした。

熱烈歓迎を受けた鑑真は、大宰府観世音寺(現在の福岡県)や東大寺で「授戒(じゅかい)」を行います。
翌年には東大寺に授戒施設「東大寺戒壇院(かいだんいん)」を建立。
授戒制度が整ったため、自称僧侶は居なくなり、風紀の乱れは劇的に改善しました。
758年、天皇の配慮により任を解かれ、自由の身になります。
翌年には新田部親王(にいたべしんのう)の旧宅地が与えられ、
戒律を学び身につけるための施設として唐招提寺を創建します。
※新田部親王(にいたべしんのう)…天武天皇の息子
また「悲田院」を作り、貧しい人や孤児を助ける活動を熱心に行いました。
唐招提寺で4年過ごし、76歳で亡くなりました。
唐招提寺の歴史

759年 唐招提寺を建てる
8世紀後半 弟子の如宝(にょほう)が唐招提寺を完成させる1270~1287年 修理修繕が行われる
1692年~ 金堂・仏像が修理される地震と火災で多くの建物が失われる
1900年~ 解体修理が行われる
1998年 「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録
(平成10年)
2000年 金堂平成大修理が始まる(約10年間)
(平成12年)
創建された当時は講堂といくつかの建物があるのみ。
鑑真の没後、弟子の如宝(にょほう)が金堂などを建て、唐招提寺を完成させました。
地震や火災により建物が焼失してしまいますが、改修と再建を繰り返し、今の姿となっています。
唐招提寺 建築の特徴
唐招提寺を観光する前に知っておきたい、建物の特徴・見どころを紹介します。
国宝 「金堂」の建築・特徴
唐招提寺最大の見どころ「金堂・こんどう」です。
南大門をくぐると、緑豊かな参道と重厚な金堂が見えます。

高さ 17.7m
奥行 14.6m
幅 28m
建立 8世紀後半(奈良時代)
寄棟造、本瓦葺き
金堂は鑑真和上が亡くなった後、弟子の如宝(にょほう)によって建てられました。
奈良時代に建立された、唯一現存する「金堂」として有名です。
創建されて1200年以上経ちますが、多くの部材が創建当時のものです。
※部材…柱や組物など
文化史でいえば、平城京を中心とする「天平時代」のものです。
屋根の形は寄棟造
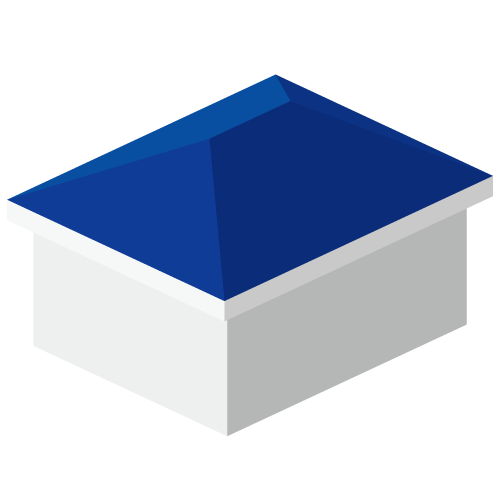
こちらが寄棟造(よせむねづくり)の屋根です。
屋根面が4方向に傾斜しています。
天平時代の屋根は「勾配が穏やかで軽快」という特徴がありますが、金堂は逆。立派な屋根が重厚感を演出しています。
その理由は江戸時代(元禄)に行われた改修です。
雨水の水はけを良くするため屋根が2m高くなり、現在の重厚な屋根となりました。
吹き放し・三手先斗栱

金堂の全面は「吹き放し」
壁はなく、八本の柱が立っている空間。
重厚さが感じられる一方で、吹き放しの柱により開放感や明るさもあります。
この柱、実は「エンタシス」です。柱の太さをよ~く見ると、中央が一番太くなっていますね。下から見上げた時に柱が真っ直ぐに見える視覚効果があります。
また列柱の柱間は中央ほど広く、外側は狭くなっています。
それにより強度が増し、建物をより大きく見せる効果があるそう。
また、三手先斗栱(みてさきときょう)という立派な組物が多く使われています。
三手先斗栱は三段の組物で、重い屋根をしっかり支えています。
美しさの秘密は黄金比
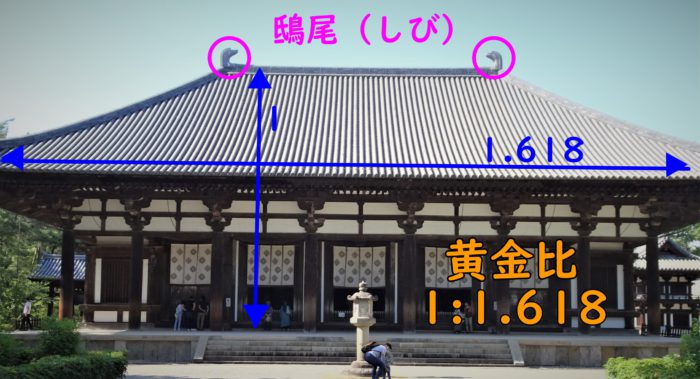
金堂は「黄金比」で作られています。
黄金比とは人間にとって最も美しいと感じる比率のこと。
金堂の縦横の長さは、黄金比の1:1.618となっています。
パルテノン神殿、パリの凱旋門、エジプトのピラミッド、金閣寺なども実は黄金比で作られています。
鴟尾(しび)
金堂の屋根の上にある「鴟尾・しび」も有名です。
大陸から伝わった屋根の装飾品であり、火除のおまじないであり、雨から屋根を守るもの。
西側の鴟尾(しび)は創建時のものでしたが、損傷が激しいため平成の大修理で取替えられました。創建時の鴟尾は新宝蔵(しんほうぞう)で見学可能です。
国宝 「講堂」の特徴・建築

建立 760年頃(奈良時代)
入母屋造、本瓦葺き
平城宮内にある東の朝集殿を朝廷から譲り受け、こちらに移築、寺院用に改造されました。
唯一現存する天平時代の宮殿として大変貴重です。
※朝集殿(ちょうしゅうでん)…家来の控室
仏教や戒律を研究し伝授するための施設として、最初に建てられました。
新宝蔵ができるまでは、多数の仏像が置かれていました。
講堂内に安置されている仏像
・弥勒如来坐像(鎌倉時代/重要文化財)
・持国天立像(奈良時代/国宝)
・増長天立像(奈良時代/国宝)
戒壇

こちらが「戒壇・かいだん」、石段のみが鎌倉時代のもの。
戒壇とは正式な僧になるための儀式、授戒(じゅかい)が行われる場所です。
鑑真は授戒により日本仏教を救い、正しく戒律を伝えることで立派な僧を輩出しました。
鑑真和上の日本や仏教への思いが感じられる場所です。
国宝「宝蔵・経蔵」の特徴・建築

建立 奈良時代(8世紀)
寄棟造 本瓦葺 校倉
北側が宝蔵、南側が経蔵。
宝蔵(ほうぞう)とはその名の通り、宝を収めておく倉庫。
経蔵よりやや大きく、唐招提寺創建時に建てられました。
経蔵(きょうぞう)は経典を収めておく倉庫。
新田部親王(にいたべしんのう)宅の米倉を改造したもの。
経蔵は唐招提寺で最も古い建物であり、日本最古の校倉造の建物です。
校倉造の代表作は東大寺正倉院。
高床、井桁 (いげた) を組んで壁を作る、保存に良いとされる建築物です。
観光ルート解説記事
拝観料・営業時間・お問い合わせ
・拝観料
大人 1,000円
高校生 400円
中学生 400円
小学生 200円
団体割引あり
※詳細はこちら(唐招提寺ホームページ)
・営業時間 定休日
8:30~17:00
定休日 なし
・施設情報(トイレなど)
トイレ・売店あり
・お問い合わせ
0742-33-7900
※最新情報はこちら(唐招提寺公式ホームページ)
ツアーの紹介
奈良の見どころをバス、タクシーで巡るツアーもおすすめです。
・現地出発のツアーなら「ベルトラ」
奈良 観光ツアー
・プランが豊富!ツアーで楽しむなら「クラブツーリズム」
話題の世界遺産や大古の歴史を楽しむ旅!クラブツーリズムの近畿旅行
※右上のメニュー(横棒3本が縦に並んでいるマーク)をクリック。
表示されたページの検索BOXに「唐招提寺」と入力し検索する方法もあります。

















税収は減るし、風紀は乱れるし…困ったものだ。